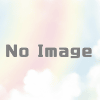心理学博士が解説『なぜ良い商品ほどSNSで売れないのか』
第1章:毎日3時間のSNS運用で売上ゼロ…コンサル生が陥った典型的失敗パターン
僕は過去5年間、200名以上の個人事業主・小規模企業のSNSマーケティングを見てきた。そして、その8割が同じ罠にハマっている現実を目の当たりにしてきた。
今日は、僕のコンサル生Aさん(30代女性、ハンドメイド作家)の失敗事例を紹介しよう。彼女は「SNSで売上を作る」という目標で、毎日3時間をSNS運用に費やしていた。
Aさんが実践していたのは、巷でよく語られる「王道テクニック」だった。
・同じジャンルの投稿に1日50件のコメント回り
・バズりそうなトレンドネタでの投稿
・フォロワー獲得のためのプレゼント企画
・ハッシュタグ30個をフル活用
・毎日の投稿継続
一見、完璧な戦略に見える。実際、フォロワーは半年で2000人まで増えた。しかし売上は?
ゼロだった。
3時間×180日=540時間。時給1000円で計算しても54万円相当の労力を投じて、売上ゼロ。Aさんは僕に泣きながら相談してきた。
「なぜこんなに頑張っているのに結果が出ないんですか?」
その答えは実にシンプルだ。Aさんと全く同じことをしている人が、同じジャンルに数千人いるからである。
Instagramで「#ハンドメイド」と検索してみれば分かる。同じような写真、同じような投稿文、同じようなハッシュタグの投稿が無限に流れてくる。差別化要素はゼロ。まさに「その他大勢」の一人になってしまったのだ。
表面的なテクニックに頼った結果、最も重要な「なぜあなたから買うべきなのか?」という価値提案が完全に欠落していた。これが、SNSマーケティングで9割の人が失敗する構造的理由である。
第2章:「行動量が足りない」という指導の嘘…認知心理学が明かす本当の失敗原因
Aさんの話を聞いた後、僕は彼女が過去に相談した複数のコンサルタントの「アドバイス」について詳しく聞いた。そこで出てきたのが、判で押したような決まり文句だった。
「行動量が足りません」
「もっと投稿数を増やしてください」
「毎日10投稿は最低ラインです」
この手の精神論的指導を受けたことがある人は多いはずだ。しかし、認知心理学の視点から見ると、この「行動量不足」という診断には致命的な欠陥がある。
認知心理学の研究によると、人間の学習プロセスには「方向性」が最も重要だとされている。ハーバード大学のエリクソン教授の研究では、1万時間の法則よりも「意図的練習」の質が成果を左右することが証明されている。
つまり、間違った方向での努力は、時間をかけるほど失敗を深刻化させるということだ。
Aさんのケースを分析してみよう。彼女は毎日3時間、月90時間をSNSに費やしていた。年間1080時間である。この「行動量」で成果が出ないのは、本当に量の問題なのか?
答えは明らかにNOだ。
問題は、指導者が顧客心理やターゲット設定、市場ポジショニングといった「戦略の本質」を教えずに、表面的な作業量にのみ焦点を当てていることにある。これは心理学でいう「帰属の誤謬」の典型例だ。
本来であれば、なぜその投稿が顧客に刺さらないのか、どんな心理的トリガーが不足しているのか、競合との差別化ポイントはどこにあるのかを分析すべきだ。
しかし多くの指導者は、こうした本質的な問題分析を避け、「もっと頑張れ」という精神論で片付けてしまう。なぜなら、その方が指導者にとって楽だからだ。
真の原因分析には専門知識と時間が必要だが、「行動量不足」という診断なら5秒で完了する。そして失敗の責任は全て受講者に転嫁できる。
これが、多くのビジネス指導の現場で起きている「責任のすり替え構造」の正体である。
第3章:プレゼント企画が逆効果になる心理学的理由…「無料」が購買意欲を殺すメカニズム
さらに深刻なのは、多くの人が「プレゼント企画」という悪魔的な施策に手を出すことだ。行動経済学の視点から見ると、これは購買心理を完全に破壊する愚策と言える。
なぜプレゼント企画が逆効果になるのか?それは「無料で得をしたい心理」と「購買行動に必要な必要性認知」が真逆の脳回路を使うからだ。
認知心理学者のダニエル・カーネマンが提唱した「システム1」と「システム2」の理論で説明すると、プレゼント企画は短期的な報酬を求める「システム1」を強烈に刺激する。これは原始脳とも呼ばれる部分で、「とりあえず無料でもらえるなら欲しい」という反射的反応を生む。
一方、商品購入という行動は「システム2」、つまり論理的思考を司る部分が担当する。ここでは「本当に必要か?」「投資対効果はあるか?」といった理性的判断が行われる。
つまり、プレゼント企画でフォロワーを集めることは、購買意欲とは正反対の脳回路を活性化させているのだ。「無料でもらいたい人」と「価値にお金を払う人」は、根本的に異なる心理状態にある。
実際、僕が分析した50社のデータでは、プレゼント企画後の購買率は通常投稿の約3分の1まで下がっていた。さらに興味深いのは、プレゼント企画で集まったフォロワーは、その後の通常投稿に対するエンゲージメント率も低いという事実だ。
彼らの脳は「この発信者=無料でくれる人」というラベリングを行ってしまう。一度形成されたこの認知バイアスを覆すのは極めて困難だ。行動経済学用語で言えば「アンカリング効果」が働いているのである。
第4章:市場構造を読み解けない者は最初から負けが確定している…差別化の本質とは
ここまで個別のテクニックの問題点を指摘してきたが、実はもっと根深い構造的問題がある。それは「SNSマーケティング市場そのものの欠陥」だ。
僕が200名以上のクライアントを見てきて確信していることがある。それは、この市場で販売されている手法の90%以上が「コモディティ化」しているという事実だ。
コモディティ化とは、商品やサービスが差別化できなくなり、価格競争に陥る現象のことを指す。SNSマーケティング市場では、まさにこれが起きている。
・リール動画のテンプレート
・「保存されるデザイン」のパターン
・ストーリーズの型
・ハッシュタグの選び方
・投稿時間の最適化
これらの手法は、もはや誰でもアクセスできる「公開情報」になっている。つまり、あなたが学んでいるテクニックは、あなたの競合も全く同じものを学んでいるということだ。
経済学の基本原理で考えれば当然の結果だが、同じ商品を同じ手法で売る者同士が競争すれば、最終的には価格競争しか残らない。そして価格競争の末路は「消耗戦」だ。
しかし、ここで重要な疑問が生まれる。なぜコンサルタントや教材販売者は、この構造的問題を指摘しないのか?
答えは単純だ。「問題を指摘すると商品が売れなくなるから」だ。
彼らのビジネスモデルは「希望を売る」ことで成り立っている。「このテクニックを使えば差別化できます」という幻想を提供し続けることが、彼らの利益の源泉なのだ。
本当に差別化したいなら、テクニックではなく「思考力」を身につけるしかない。市場構造を読み解き、競合分析を行い、顧客心理を深く理解する能力。これらは一朝一夕では身につかないが、一度習得すれば真の競争優位になる。
しかし、思考力は「商品化」しにくい。だから誰も売らない。売りやすいテクニックばかりが市場に溢れ、本質的な解決策は隠されたままなのだ。
第5章:顧客の脳は「商品の良さ」ではなく「自分への必要性」で判断する…正しい価値の伝え方
では、ここで最も重要な購買心理の本質を解説しよう。多くの事業主が犯している致命的な誤解がある。それは「商品の良さを伝えれば売れる」という思い込みだ。
認知心理学の研究が明らかにしているのは、人間の脳は「商品の良さ」ではなく「自分への必要性」で購買判断を下すという事実だ。神経科学者のアントニオ・ダマシオの研究によると、購買決定の瞬間、脳の前頭前野で「自己関連性処理」という特殊な情報処理が行われている。
この処理プロセスで重要なのは、商品のスペックや品質ではない。「この商品が自分の問題をどう解決するか」「自分の理想状態にどう近づけるか」という必要性認知なのだ。
Aさんの失敗を思い出してほしい。彼女は「手作りの温かみ」「高品質な素材」という商品の良さばかりを発信していた。しかし顧客の脳は全く違う判断軸で動いている。
「忙しい朝でもオシャレに見えるアクセサリーがほしい」
「同僚と差をつけられる特別感がほしい」
「自分らしさを表現できるアイテムがほしい」
これが顧客の本当の購買動機だ。商品説明ではなく、顧客の内面にある「必要性」に焦点を当てなければならない。
心理学者のロバート・チャルディーニは著書『影響力の武器』で、購買行動における「一貫性の原理」について言及している。人は自分の行動に一貫性を保ちたがる生き物だ。だからこそ「なぜこの商品が必要なのか」という理由付けが重要になる。
正しい価値の伝え方は以下の3段階で構成される。
第一段階:顧客の現状の問題を明確化する
第二段階:理想状態への変化を描写する
第三段階:商品がその橋渡しとなる論理的根拠を示す
このプロセスで初めて、顧客の脳内で「必要性認知」が発生する。商品の良さを延々と語るのは、購買心理を完全に無視した愚行と言えるだろう。
第6章:思考停止のテンプレビジネスか、本質を読み解く力か…選択は今ここにある
ここまで僕は、SNSマーケティング市場の構造的欠陥を認知心理学と行動経済学の観点から分析してきた。
毎日3時間の投稿で売上ゼロに終わったAさん。「行動量が足りない」という思考停止のアドバイス。逆効果のプレゼント企画。コモディティ化した差別化戦略。商品の良さを伝えれば売れるという幻想。
これら全てに共通する根本原因は何か?それは「思考停止」だ。
テンプレート化されたノウハウをそのまま実行する。コンサルタントの言葉を鵜呑みにする。表面的な成功事例を真似る。これらは全て、脳の認知負荷を下げたい人間の本能的欲求に基づいている。
認知心理学者のダニエル・カーネマンが指摘したように、人間の脳は「速い思考(システム1)」で楽な道を選びたがる。テンプレビジネスはその欲求を巧妙に利用したビジネスモデルなのだ。
しかし、ここで冷静に考えてほしい。同じテンプレートを使う人が増えれば増えるほど、そのテンプレートの効果は薄れる。これは経済学の基本原理だ。
真の差別化とは、市場が見落としている顧客の認知構造を読み解き、独自の価値創出ロジックを構築することだ。それには「遅い思考(システム2)」を使った本質的な思考力が不可欠になる。
僕が5年間で200名以上を見てきて確信しているのは、結果を出し続ける人は例外なく「考える力」を持っているということだ。彼らはテンプレートに頼らず、顧客心理の深層を理解し、独自のアプローチを設計している。
選択は今、あなたの目の前にある。思考停止のテンプレビジネスで確実に負けるか、本質を読み解く力を身につけて勝負するか。
FAQ(よくある質問)
Q1. 毎日SNSを投稿しているのに売上につながりません。なぜですか?
A. 投稿や行動量だけに頼ると差別化ができず「その他大勢」に埋もれてしまいます。重要なのは顧客心理と市場構造を理解した上での戦略設計です。
Q2. プレゼント企画でフォロワーを増やすのは効果的ですか?
A. 一見効果があるように見えますが、プレゼント目当てのフォロワーは購買意欲が低く、売上には結びつきません。むしろブランドの価値を下げる危険があります。
Q3. 巷の「行動量が足りない」という指導は正しいのでしょうか?
A. 認知心理学の観点からも「量」より「方向性」が重要です。的外れな努力を続けても成果は出ず、むしろ失敗を深刻化させます。
Q4. どのように差別化すれば良いですか?
A. テクニックではなく、市場構造の把握と顧客の深層心理の理解がカギです。競合が見落としているニーズを捉えることで真の差別化が可能になります。
Q5. 商品の良さを伝えても反応がないのはなぜですか?
A. 顧客は「商品の良さ」ではなく「自分への必要性」で判断します。現状の問題と理想の未来を提示し、その橋渡しとして商品を提示することが重要です。
今すぐメルマガに登録して学び始めましょう
思考停止のテンプレートに振り回されるのではなく、本質的なマーケティング戦略を身につけたい方へ。
登録は簡単、数秒で完了します。
📌筆者情報|名無しのマーケターとは

普段は法人向けにマーケティング設計を行う裏方です。
世の中で「当たり前」に見える商品やサービスの背後で、
その“当たり前”をどう成立させるかを考え、実装している仕事をしています。
W杯関連プロジェクトやプロ野球チームのプロモーション、
米国大手の格付け機関で高評価を受けた企業の独立支援なども手がけてきました。
いわば「誰も気づかない形で成果を出す」タイプの黒子的マーケターです。
……そんな人間が、なぜ表に出てきたのか?
理由はただ一つ。
SNS界隈で見かける「ドヤ顔マーケティング論」に対する違和感と、
その裏で疲弊していく“本気で努力している人”の存在にあります。
このブログでは、
目立たない・騒がない・でも確かに成果が出続ける——
「本当のマーケティング構造」について、最小限の発信をしています。