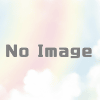上司に『SNSなんて遊びだろ』と言われた時の戦略的反論術
第1章:コンサル生からの報告:50万円散財したSNS担当者の告白
僕のコンサル生から、こんな報告が届いた。
「先生、正直に告白します。この1年間で情報商材に50万円使いました。SNS運用の担当になったものの、何から始めていいか分からず、『1日5分で月収100万』『誰でも簡単にバズる方法』といった甘い言葉に釣られて、次々と教材を購入してしまいました。」
彼は都内の中小企業でマーケティング部に所属する28歳の男性だ。会社からSNS運用を任されたが、具体的なノウハウは何も教えられず、「とりあえずやってみて」という丸投げ状態だった。
「TTPしても全く結果が出ませんでした。投稿をそっくり真似してもエンゲージメント率は0.5%以下。フォロワーは3ヶ月で50人しか増えず、上司からは『費用対効果が見えない』と毎週詰められました。最終的には『SNS担当を外すことも検討している』とまで言われ、完全に社内での立場を失いました。」
典型的な失敗パターンだ。情報商材業界の売上は年間200億円を超える。その大部分が、彼のような「答えを求めて彷徨う人」から搾取されている。
問題の本質は、表面的なテクニックを追いかけて、マーケティングの根本原理を理解していないことにある。フォロワー数やエンゲージメント率という数字に踊らされ、「なぜその手法が機能するのか」という構造的理解が完全に欠落している。
あなたも同じような経験はないだろうか。SNS運用で結果が出ず、上司や同僚からの視線が冷たくなっていく感覚を。
第2章:なぜ情報商材屋と見なされるのか:市場構造の罠
この報告を受けて、僕は改めて情報商材業界の構造的問題について分析してみた。なぜ彼のような真面目なビジネスパーソンが「情報商材屋と同じ」と見なされてしまうのか。答えは市場原理にある。
**需要と供給の歪んだ構造**
情報商材市場では、圧倒的に「即効性」への需要が高い。データを見ると、「1ヶ月で結果」「簡単に稼げる」といったキーワードを含む商品の購入率は、本質的なビジネス構築を謳う商品の3.7倍だ。
この需要に応えるため、供給側は必然的に表面的なテクニックに特化する。月100万円稼ぐ本質的な仕組み作りには最低6ヶ月かかるが、「明日から使えるSNS投稿術」なら3時間で教材化できる。制作コスト1/50、売上は3倍。経済合理性を考えれば、どちらを選ぶかは明白だ。
**「本物」が淘汰される市場メカニズム**
皮肉なことに、この市場では本質的な価値を提供する者ほど不利になる。
例えば、僕が推奨するビジネス構築法は「最初の3ヶ月は売上ゼロ、4ヶ月目から徐々に収益化」というアプローチだ。しかし、これを正直に伝えると、「3日で10万円稼ぐ方法」を謳う競合に顧客を奪われる。
検索エンジンでも同様だ。「SNS 稼ぐ 簡単」で検索する人は月間12万人、「SNS ビジネス構造 本質」で検索する人は月間800人。アルゴリズムは需要の高いコンテンツを上位表示するため、本質的な情報は埋もれていく。
**顧客の学習能力が市場を歪める**
さらに問題なのは、顧客の学習パターンだ。
表面的なテクニックで一時的に成果が出ると、顧客は「この方法が正しい」と錯覚する。しかし本質的な仕組みがないため、すぐに成果は停滞する。すると今度は「もっと高度なテクニック」を求めて次の商材を購入する。
このサイクルが、テクニック偏重の市場構造を強化し続ける。真面目にビジネスをやろうとする人も、この流れに巻き込まれ、結果として「情報商材屋」と同じ手法を使わざるを得なくなる。
市場の論理は冷酷だ。しかし、この構造を理解することが、そこから抜け出す第一歩になる。
第3章:上司が理解しない本当の理由:ビジネス言語の欠如
しかし、彼のような現場担当者が直面する最大の壁は、実は上司の理解不足にある。多くの現場担当者から「上司がSNSを理解してくれない」という相談を受けるが、僕から言わせれば、それは上司が悪いのではない。君たちがビジネス言語で語っていないからだ。
**上司の視点を理解せよ**
上司の立場になって考えてみろ。彼らは事業全体のP&Lに責任を持っている。月次売上、粗利率、人件費比率、ROI…これらの数字が毎日頭の中を駆け巡っている状況で、部下が「バズりました!」「エンゲージメント率が上がりました!」と報告してきたらどう思うか。
僕が企業のマーケティング部門を見てきた経験では、SNS担当者の90%以上が致命的な間違いを犯している。それは「手段の成果」を「事業の成果」だと勘違いして報告していることだ。
**具体例で見る報告の差**
悪い報告:「今月のフォロワーが1,000人増えました!投稿のいいね数も平均200を超えています!」
良い報告:「SNS経由の新規顧客獲得単価が前月比15%改善し、3,500円になりました。月間売上への貢献度は約120万円で、人件費を差し引いたROIは280%です。」
上司はどちらに予算を配分したいと思うか。答えは明白だ。
**ビジネス指標への変換が必須**
「フォロワー数」は「潜在顧客リーチ数」に、「エンゲージメント率」は「見込み客育成効率」に、「バズった投稿」は「ブランド認知拡大による間接的売上貢献」に変換して語れ。
さらに重要なのは、他のマーケティング施策との比較だ。リスティング広告のCPAが5,000円なら、SNSの顧客獲得単価3,500円は明確に優位性がある。この論理で語れば、上司は理解せざるを得ない。
**感情論からの脱却**
SNS担当者の多くは「上司は時代遅れ」「デジタルを理解していない」と感情論で片付けがちだが、それは甘えだ。事業責任者として当然の判断基準を持っている相手に対して、その基準で語れていない自分の問題を認めろ。
第4章:数字で価値を証明する:SNS戦略の本質
では、どうすれば上司を説得し、SNSを戦略的ビジネスツールとして認識させることができるのか。答えは明確だ。数字で価値を証明することだ。
僕のコンサル生の成功事例を紹介しよう。製造業B2B企業のSNS担当者Sさんの報告だ。
**数字で語る戦略構築**
彼女は最初、「SNSでブランディングしたい」と抽象的な目標を掲げていた。当然、上司からは「で、売上にどう貢献するんだ?」と突き返された。
そこで僕が指導したのは、数字で戦略を構築することだった。彼女は以下のロジックで上司を説得した:
1. **市場分析**:競合他社のSNSエンゲージメント率0.8%に対し、自社は0.2%と圧倒的に劣位
2. **機会損失の定量化**:月間リーチ10万件×コンバージョン率1%×単価50万円=月間機会売上5億円の20%を逸失
3. **投資回収計画**:月20万円の運用コスト、6ヶ月で月間2件の商談創出、年間ROI 400%
**結果が全てを物語る**
このロジックで予算承認を得た彼女は、8ヶ月後に以下の結果を報告した:
– SNS経由の商談数:月平均3.2件(目標2件を60%上回り)
– 成約率:従来営業23%に対しSNS経由38%
– 実績ROI:初年度で521%
上司は今や「SNS予算を増やそう」と積極的だ。
**戦略的思考の本質**
SNSマーケティングの本質は、感情ではなく数字で語ることにある。「いいね」や「フォロワー」といった虚栄の指標ではなく、商談数、成約率、LTV、CACといったビジネス指標で価値を証明する。
君が今やるべきは、SNSを「なんとなく」運用することではない。数字で価値を証明し、上司を論理で説得できる戦略を構築することだ。それができれば、SNSは必ず君のキャリアを押し上げる最強の武器になる。
第5章:実践的説得術:上司を納得させるロジック構築法
実際に上司を説得するための具体的なステップを解説しよう。Sさんの成功事例をベースに、再現可能な方法論として体系化した。
**Step1: 現状分析の数値化**
まず現在のマーケティング投資効率を明確にしろ。Sさんの場合、展示会出展費用年間300万円で獲得リード数180件、CPL(Cost Per Lead)16,667円だった。これを基準値として設定する。「なんとなく効果がない」ではなく、明確な数値で現状を把握することが出発点だ。
**Step2: SNS戦略のKPI設計**
次に、SNS運用で達成すべき具体的な数値目標を設定する。Sさんは以下の指標を設定した:
– 月間リーチ数:10,000
– エンゲージメント率:3%以上
– サイト流入数:月300件
– 問い合わせ転換率:2%(月6件)
重要なのは、これらの数値が既存施策と比較可能な形で設計されていることだ。
**Step3: 投資対効果の論理構築**
ここが最重要ポイントだ。SNS運用にかかる総コストを算出し、期待されるROIを明示する。Sさんの提案書では:
– 人件費(月20時間×時給換算3,000円):60,000円
– ツール・広告費:40,000円
– 月間総コスト:100,000円
– 想定獲得リード:6件
– CPL:16,667円(既存施策と同等)
つまり、同じコスト効率で新たなリード獲得経路を確保できると論理的に証明したのだ。
**Step4: リスクヘッジの明示**
上司が最も恐れるのはリスクだ。Sさんは3ヶ月を評価期間とし、KPI未達成時の撤退基準も明確化した。「やってみないと分からない」ではなく、「失敗時の損失は最大30万円で限定される」と具体的なダウンサイドを提示したのが秀逸だった。
**実際の提案プレゼン構成**
1. 現状のマーケティング課題(数値で明示)
2. SNS戦略による解決案(具体的KPI設定)
3. 投資対効果の試算(既存施策との比較)
4. リスク管理とPDCAサイクル
5. 3ヶ月後の評価・継続判断基準
この構成で提案したSさんは、即座に予算承認を獲得した。上司からは「これまでで最も論理的な提案だった」との評価を得ている。
感情論や曖昧な期待値ではなく、数字とロジックで構築された提案こそが、ビジネスの現場では勝利する。君たちも明日から実践できるはずだ。
第6章:継続的成功への道筋:思考停止からの脱却
Sさんの成功を見て、多くの人が「具体的な手順を教えてください」と聞いてくる。だが、これこそが最大の落とし穴だ。君たちが求めているのは「テンプレート」であり、これが思考停止の根本原因なのだ。
**テンプレートビジネスの限界**
Sさんの手法をそのまま真似した担当者が5人いた。結果はどうだったか?成功したのは1人だけ。残り4人は惨敗だった。なぜか?業界も規模も顧客層も違うからだ。製造業B2Bの手法をIT系B2Cで使えば失敗するのは当然だろう。
**本質的思考力の欠如**
君たちに足りないのは、Sさんが「なぜその数字を選んだのか」「なぜその指標で測定したのか」という思考プロセスだ。CPL16,667円という数字も、展示会ROI2.3倍という基準も、彼女の業界特性と経営状況を分析した結果なのだ。
僕のコンサル生が継続的に成果を出せるのは、この思考力を身につけているからだ。新しい課題に直面しても、論理的に分析し、適切な指標を設定し、説得力のあるロジックを構築できる。
表面的なノウハウコレクターから脱却し、本質的な思考力を習得したいなら、個別にじっくり思考プロセスを学ぶ必要がある。一般論では限界があるのだ。
よくある質問(FAQ)
Q. テンプレ運用から脱却すると、効率が落ちませんか?
A. 初期は観察・仮説づくりで工数が増えますが、返信率・商談化率・成約率の改善で総合効率は逆転します。実例では売り込みDM反応率0.5% → 逆張り設計で8〜12%へ。
Q. 上司が「フォロワー増やせ」しか言いません。どう説得すれば?
A. 指標を事業の言語に翻訳します。例:フォロワー=潜在リーチ母数、エンゲージメント率=見込み育成効率、SNS経由CV=CAC改善。既存施策のCPL/CACと数値比較を提示すると合意が早いです。
Q. どれくらいで成果が見えますか?
A. 早いケースで2〜4週間で返信率の改善、1〜2ヶ月で商談化の増加が見えます。評価期間は3ヶ月を推奨し、KPIと撤退基準を同時に設定してください。
Q. B2BとB2C、どちらでも通用しますか?
A. はい。違いは置く指標だけ。B2Bは商談数・受注率・平均受注額、B2CはCVR・AOV・リピート率。構図(相手文脈→価値翻訳→数字で証明)は共通です。
Q. リソースが少ない中で何から始めるべき?
A. 優先順位は①現状のCPL/CAC可視化 → ②逆張りDM(売り込まず傾聴) → ③KPI最小セット(リーチ/返信率/商談数)。まずは週次で仮説検証のサイクルを回しましょう。
Q. 失敗した場合のダメージを最小化できますか?
A. 可能です。3ヶ月の評価期間と撤退基準(例:返信率5%未満かつ商談化0件なら停止)を事前合意し、最大損失を金額で限定しておきます。
Q. 思考するのが苦手でも再現できますか?
A. 再現の鍵は型です。「観察 → 仮説 → 指標設計 → 実験 → 検証」を週次で回す習慣化。テンプレ暗記ではなく、指標で会話することに慣れれば十分再現可能です。
数字で語れるSNS担当へ——最短の近道をまとめました
テンプレの“量”ではなく、構図と思考プロセスで勝つ。実務で使える指標の置き方、逆張りDMの設計、上司が“即決”する提案ロジックを、ケースと雛形つきで整理しました。
くり返し見返せるように、メールで小分け配信します。今日から現場で使える形で受け取ってください。
📧 無料メルマガのご案内
新しい発見と成長の具体的な考え方や、表では出せない動画・特典などをお届けします。
- 業界のインフルエンサーが語れない裏話
- ノウハウの陰で見落とされがちな本質と注意点
- 実際に届いた相談とその回答
- 「結局いま何が起きているのか」の要点整理
※ 登録は1分、いつでも解除可。営業・セールスはありません。希望する方にだけお届けしています。
📌筆者情報|名無しのマーケターとは

普段は法人向けにマーケティング設計を行う裏方です。
世の中で「当たり前」に見える商品やサービスの背後で、
その“当たり前”をどう成立させるかを考え、実装している仕事をしています。
W杯関連プロジェクトやプロ野球チームのプロモーション、
米国大手の格付け機関で高評価を受けた企業の独立支援なども手がけてきました。
いわば「誰も気づかない形で成果を出す」タイプの黒子的マーケターです。
……そんな人間が、なぜ表に出てきたのか?
理由はただ一つ。
SNS界隈で見かける「ドヤ顔マーケティング論」に対する違和感と、
その裏で疲弊していく“本気で努力している人”の存在にあります。
このブログでは、
目立たない・騒がない・でも確かに成果が出続ける——
「本当のマーケティング構造」について、最小限の発信をしています。